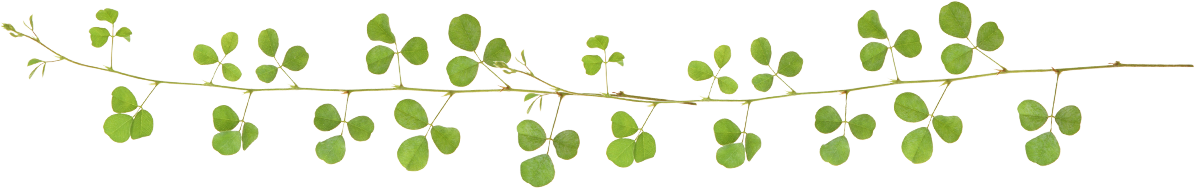茨木のり子と谷川俊太郎の
「言葉」についての言及から
思った事が
もう一つあります。(いっこめはこの投稿)
子どもらが小さい頃、
言葉で伝える大切さを
いつも伝えていた時期が
あって。
なぜならそれは
言葉の表現によって
本人が感じる感情の豊かさが
圧倒的に変わると思っていたから。
今のように
いいね!悪いね!
二択しかないとか
「ムカつく」
「かわいい」
とかそんな一言を
いつも使ってたら
自分のもっと深い感情が
自分で分からなくなる
モヤモヤとした
この感情、
どう表現する?
というのは
小さいころからの積み重ねで
たくさん経験して
いろんな感覚を知って
いろんな感情を受け取って
分かるもの。
いろんな「ムカつく」があって
いろんな「かわいい」があって
それ以外もあること。
そのために
外で自然と触れ合って
絵本を読んで
絵を描いて
人や何かとコミュニケーションを取る
自分を理解するために
言葉を尽くして
思ってる事や
感じてる事を
言葉に充てることは
とても大切だからね
もし言葉が苦手でも
音で表現したり
踊りで表現したり
他の表現方法があれば良い
だけど日常に一番身近なものが
「言葉」だと思ったから、
私は子どもらに
どうおもってる?
どう感じてる?
すぐに分からないって諦めないで
なんでもいいから
言葉にしてみようね。
じっくりと待って
伝えてきたつもりです。
表現しようとトライすると
表現できなかった分も含めて
感じる心が育まれる。

(初日の出から数日遅れのご来光が美しい)
だけど今思えば
私は言葉を使うのが好きで
なんでも言葉を尽くして
伝えられるのではないかと
思っていたから
そうしていたのかも知れない。
言葉にできることなんて
目で見えるものが限られているように
そんなには多くない、
と氣付いたから。
見えるものの奥には
たくさんの
見えないエネルギーがあって
言葉の周りには
言葉にならない世界が
どこまでも広がっている。
ちっぽけな自分と、
無限の愛のエネルギー。
そんなふうに感じたから。
だから今
言葉が多すぎるのは、
私たちは
言葉に頼りすぎて、
見えるモノに頼りすぎて、
感じられるはずの
たしかに「在る」ものを
たくさん取りこぼしている
ってことだと私は思う。
それに警笛を鳴らしてくれているのが
「言葉が多すぎる」という
メッセージだと思う。
言葉は大切だけど、
その限界も知っておくことは
同じくらい大切。
それが分かって
子どもの成長と共に
私もすこしは成長できているかなぁ